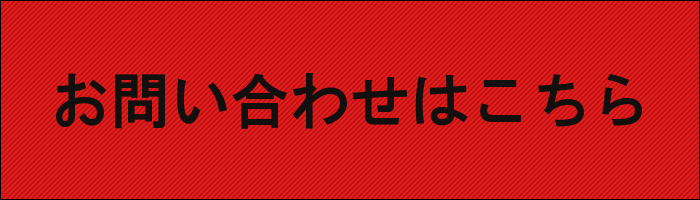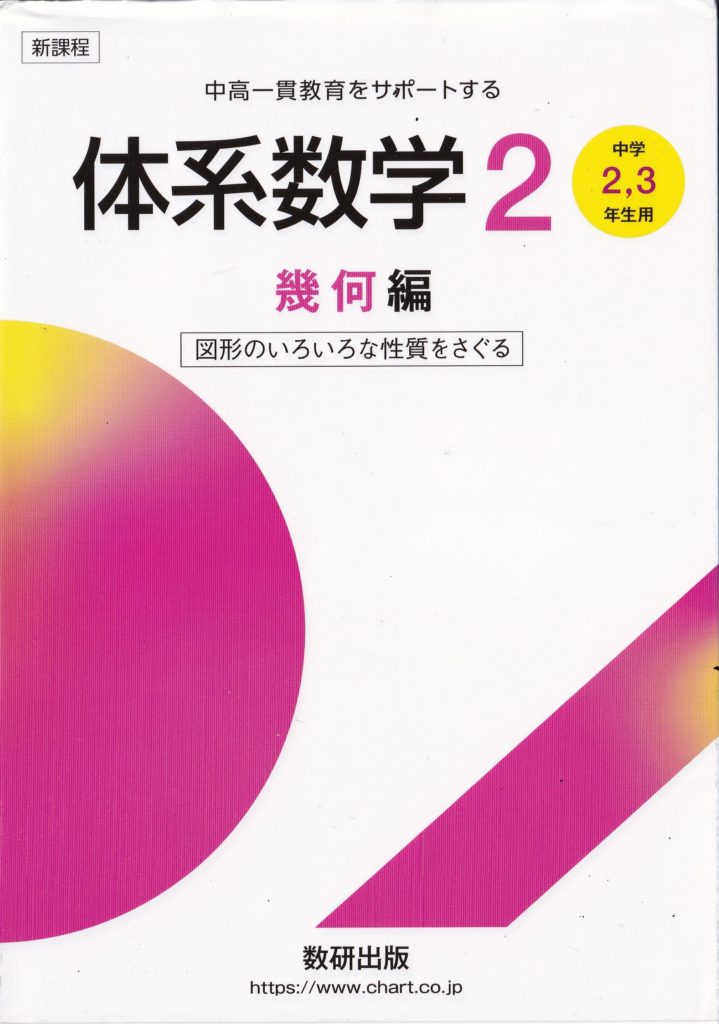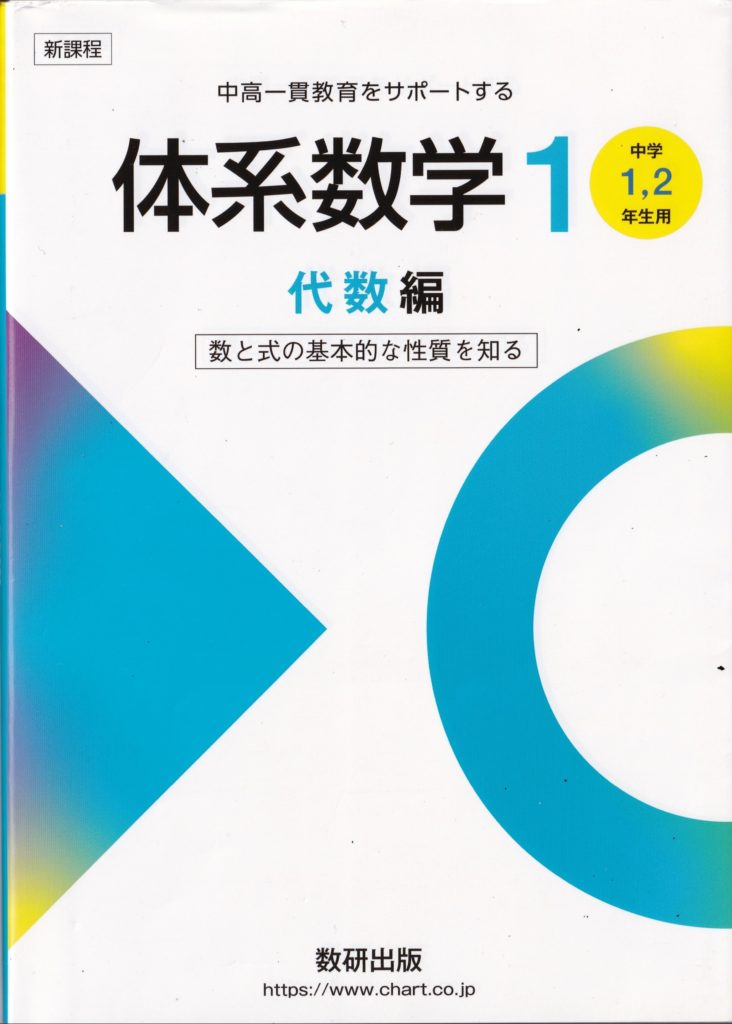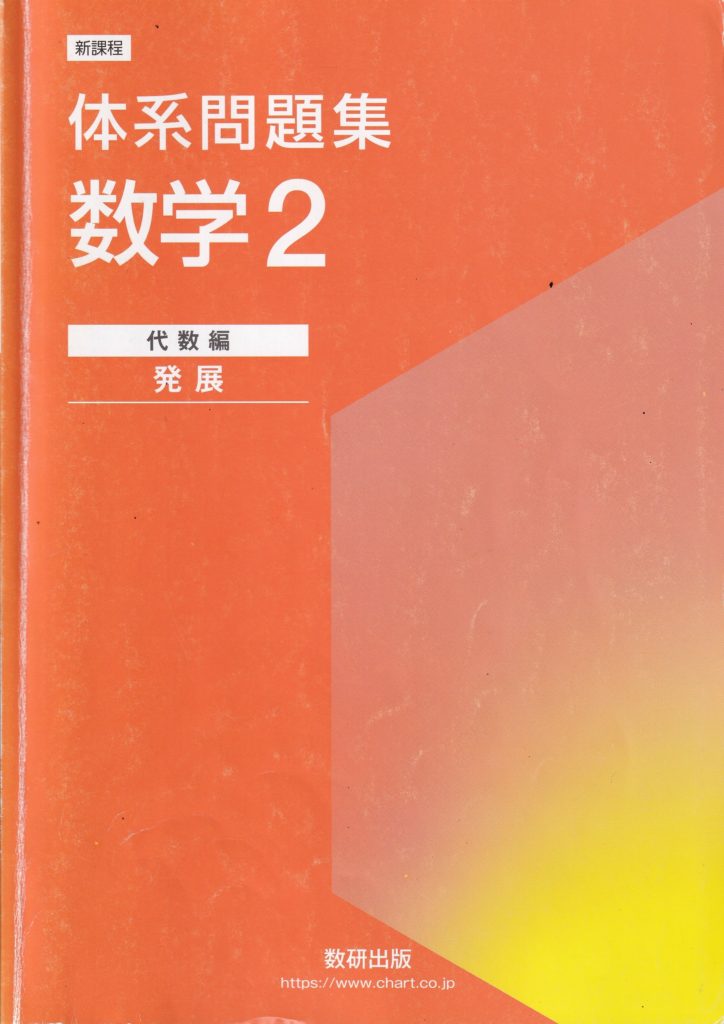個人指導シグマでは、2023年12月よりも 動画 サポートを開始しました。
最初は、数人の生徒さんに限定して動画を作ってみました。
評判は最初から上々!
約1年たって、非常に使えることが分かったのでオープンにします。
動画サポートとは何か?
問題の解説を動画でアップして いつでも見れるようにするという方法です。
1年ほど何人かの生徒さんに協力していただいて 、その効果を測定いたしました。
学年は 、中学生 が中心です。
普段使っている問題集で解説を要するような問題や 1回では分からないような問題を中心に動画を作成しました。
また、テストに出る範囲で特別な方法を使う問題の動画も作成しました。
その結果 、通常の授業 1回ではなかなか 得点に結びつかないような問題でもテストで点数を取れる様になりました。
動画は、見てわからなかったら何度も見ることが出来ます。
自分のペースで反復学習ができるようになって、理解度が格段に上がりました。
特に効果が上がったのは 、図形 や文章題 複雑な計算です。
図形の証明問題などは、出てくる事項が多いので全体を一度に把握することがなかなか困難です。
そういった時に、動画 サポートで何度も見るとだんだんと問題の解き方 っていうのが分かって来ます。
証明の問題だと全体の流れ っていうのが見えない 生徒さんがいます。
そんな生徒さんにとって、動画でのサポートがあると学習を進めやすくなります。
通常学校でもらっている問題集に関しては 、詳しい解説用の別冊のものがついています。
でも、文字で書いている 解説を読んで ちゃんと理解できない生徒さんというのがかなりの数います。
そういった 生徒さんには 動画でサポートしてあげた方が理解を進められます。
文章題に関しても、長い文章題だと要点がなかなかわからないことがあります。
手順 も複雑になるような問題も結構あります。
そういった問題でも 考え方 などを何度も解説を見ると身についてきます 。
食塩水や速さの問題などが典型的です。
やり方を忘れても 、解説を見ればいいので安心して学習を進めることができます。
こちらも 解答の文章を読んで理解できない人たちには有効です。
動画サポートの範囲
サポートの対象ですが、 基本的には数学になります。
数学でも一般的な 中高一貫校で使ってる 問題集のサポート中心です。
中高一貫校で一般的なのは、体系数学です。
体系数学のb問題や C 問題を中心に 動画にしています。
動画サポートの視聴方法
動画サポートの 動画は、 YouTube の 限定公開にアップします。
限定公開なので、動画のリンクを知らないと見ることが出来ません。
動画 サポートを希望する生徒さんには 、その動画のリンクを配布します 。(個人指導シグマの生徒さんだけです。)
YouTube ですので、 自分で見る時にはスマホでも iPad でも PC でも 見ることができます。
時間も自由で、自分のペースで見れます。
何度も繰り返し見ることも可能です。
場所も制限が有りません。
電車での通学時間 途中でも可能です。
テスト前に集中的に見る人が多いようです。
動画サポートの使い方
パター 1
まず、最初に自分で解く。
それから 答え合わせをする。
間違った問題は解説を見る。(ここで動画サポートを利用)
この流れで、 ある程度はわかるようになります。
でも、 1回で出来るようになることはそんなにはありません。
何回も繰り返すということで 、テストまでに正解率を上げることが可能になります。
パターン2
もう1つのやり方は、 もともと難しいってのわかってる問題については 最初に解説を 見てもらいます。
解説を見てから自分の手で解く という作業に入ります。
そうしないと、考えてわからない問題に時間をかけてもしょうがないですからね。
最初に見てしまえば、あとは順番を逆にして、まず問題を解き それから 解説を見る 。
これを何度も繰り返しです。
計算ミスが多い人にお勧め
動画サポートは、計算ミスが多い人にも有効です。
個人指導シグマの教室の生徒さんには、計算練習は普段からやるように言っています。
でも、なかなか上達しない人たちがいます。
それは自己流のやり方をずっと続けているからというのがあります。
正しいやり方 やもっと速くて正確なやり方っていうのを理解ことが必要です。
動画サポートを見ることで、自分の間違ったやり方を修正することができるようになります。
平均点以下の生徒さんは、代数で30点アップした人も出ています。
特に体系数学で困っている生徒さんにお勧め
個人指導シグマは、中高一貫専門の個人指導塾です。
だから、中学1・2年生は体系数学を使っている生徒さんが圧倒的に多いです。
体系数学のフォローをしてくれる塾は、そんなにありません。
個人指導シグマは、オンライン授業にも対応していて動画でフォローしているので体系数学でお困りの方にお勧めです。
動画サポートのモニターをやってもらった生徒さんも体系数学を使っている学校の人達です。
皆さん、上がり下がりは有りますが、動画サポートを始める前よりも格段に点数が取れる様になりました。
筑波大学付属中学の生徒さんにもお勧め
個人指導シグマは、文京区に有ります。
国立大学付属中学がいくつも近所にある地域です。
その中でも、筑波の生徒さんが昔から通ってきています。
筑波の数学は、普通の問題集には載ってないような問題を授業で取り上げることもあります。
そんな問題は、授業中に理解している人は少数です。
動画サポートでそんな問題を解説することで、取りにくい問題も得点するケースが増えました。
授業中の解説を動画にすることも
授業自体を録画することもあります。
と言っても、そのまま全部録画するとかなり長時間になります。
そこで、問題を解説している部分だけ切り抜いて録画しています。
こちらは、希望者だけのサービスです。
学校のプリントなどの解説に使います。
あくまでもその生徒さんのレベルに合わせての解説なので、他の生徒さんが見てもいまいちの内容になることもあります。
でも、個々の生徒さんには、レベルを合わせているので分かりやすくなっています。
動画 サポートに関しては 、動画を作るのに結構時間かかります。
それで、最大公約数的に皆さんが使うことが多い教材を対象にしています。
個人指導シグマのオンラインの授業解説をそのまま動画にすることもあります。
この場合は、その生徒さんだけに動画のリンクを渡しています。
今後、徐々にコンテンツを増やす予定です。
授業の予習動画まで出来れば、それを事前に見てもらって実際の授業は問題演習から始めたりも出来ます。
個人指導シグマは、中高一貫&国立大学付属専門の個人指導
ZOOMやスカイプなどのオンライン授業にも対応しています。
動画でのサポート付きの授業をご希望の方は、お気軽にお問合せください。