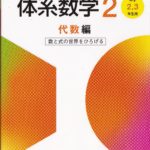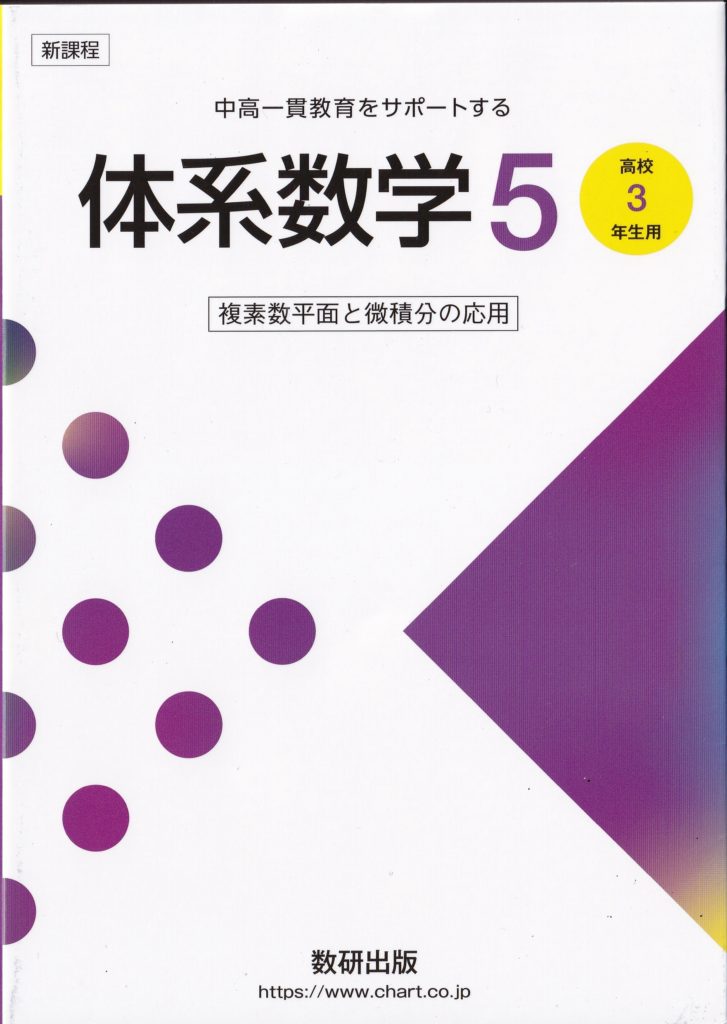
関東圏の中高一貫校では、体系数学を使っている学校が非常に多いです。
過半数を超えます。
上手く使うと効果がある一方で、ついていけなくなる人も沢山出ています。
そんな人はどうすればいいのか?
体系数学が中高一貫校で使われる理由
中高一貫校の過半数で使われている体系数学
使われるのには理由があります。
それは・・・
先取り学習に適した構成
一番の理由は先取り学習用に作られていることではないでしょうか。
体系数学1・2までで検定教科書を使っている公立中学の内容+高校生の内容の一部が学習できます。
これを中学2年生までにやってしまえば、中学3年生からは高校の教科書を使って学習できるのです。
進みの速い学校であれば、高校1年生で文系の範囲の学習が終わります。
私立文系コースを選択したの生徒さんは、高校2年生からは学校にもよりますが数学の授業が少なくなったりします。
その分を文系科目に振り分けるので、受験勉強が当然ながら進みます。
国立文系の生徒さんは、その後は問題の難易度を上げながら受験勉強をスタートです。
理系の生徒さんは、数3の内容まで当然必要です。
その場合でも高校2年生の間には、入試の範囲の学習が終わりです。
高校3年生の1学期で数Ⅲが終わる公立高校理系の生徒さんと比べると中高一貫の生徒さんは、受験勉強に割く時間が多いということになっています。
学習する順番も検定教科書とは違います。
例えば関数であれば、比例・反比例に続けて一次関数が出てきたりします。
公立中学だと中学1年と中学2年に分けて学習している分野です。
この辺りは、非常に合理的だと思います。
2次関数は、2次方程式が解けることが必要なので続けては出てきません。
体系数学2代数に入っていますので、中学2年生で学習することになります。
関西圏の学校で、中学2年生で二次関数を学習した後に高校の範囲の関数につなげているケースが有りました。
あまり見たことが無いケースですが、やろうと思えばできないことも有りません。
ちなみに、スパルタで有名な学校です。
難度の高い問題
ほとんどの学校では、問題集も一緒に使います。
同じように体系数学にも対応した問題集があります。
この問題集のレベルが検定教科書とは比べ物になりません。
問題集にも標準版と発展版があります。
が、ほとんどの学校で発展版を使っているようです。
体系問題集は、難易度によってABCに分かれていますが、Bレベルまでは解けるようにしておきたいところです。
Cレベルは、問題数も少ないので余裕がある方だけでいいと思います。(学校の方針によります。)
実際に学校のテストでも、B問題までが試験範囲になっている学校とC問題も含める学校があります。
普段の体系数学の学習法
まずは教科書
全く分からないのならば、まずは教科書です。
教科書をじっくりと読みましょう。
そのうえで例題を解いて、出来なかったら例題の解説を見てください。
例題の解説は、詳しく書いています。
例題で間違った問題は、そのすぐ下にある練習問題を解きましょう。
練習問題の解答は、教科書に別冊で付いています。(一部の学校では、ついていないそうです。)
テストが近付いたら、章末問題も必ず解きましょう。
見落としがちですがよくテストに出題されます。
学校に合わせる
体系数学に限りませんが、英語や数学は学校の進度に合わせて進めることが大切です。
体系数学であれば、問題集を解きましょう。
理想を言えば、毎日学校で学習した分だけ家に帰ってから問題集を解いてください。
これでその日やったことが復習出来て理解が進みます。
人間の記憶はあてになりません。
始めて学習した内容は、次の日には30パーセントしか覚えていないといった調査結果があります。(エビングハウスの忘却曲線)
分からないことをそのままにすると、覚えていること自体が少なくなって手が付けられなくなります。
毎日少しずつならば、そんなに量は多くありません。
部活などで十分な時間がない方はどうするのか?
体系数学問題集の■の問題だけを解いてください。
■の問題だけで一通り学習できるようになっています。
答え合わせ
解いたら答え合わせをすぐにやってください。
”そんなの当たり前じゃないか!”とおっしゃる方もいるでしょう。
でも、実際に教室で教えているものから見るとちゃんとやっていない生徒さんが目に付くのです。
問題集を1ページ解いたらそれで終わり。
答え合わせなどありません。
「なんで答え合わせやらないの?」と聞いても
「だって、全部あってるし・・・」
そんな生徒さんに限って実際に目の前で答え合わせをしてみると間違いがボロボロ出てきます。
そんな状態ですが、自分では勉強した気になっているのです。
解きっぱなしは、一番ダメなやり方です。
正しい知識をつけていかないと間違ったことを続けてしまいます。
問題を解いたらすぐに答え合わせです。
時間を置くと問題自体を忘れてしまいます。
計算ミスが多い方は、特に徹底してください。
中学1・2年の間に計算力を付けないと高校生の内容になると苦労することになります。
出来る問題と出来ない問題を区別
解けなかった問題は、チェックをつけましょう。
出来る問題とそうでない問題を区別することでその後の復習の時間を短縮できるのです。
出来る問題を何度もやっても意味がありません。
出来なかった問題を出来るようにするからこそ学力が上がるのです。(オセロみたいですね。)
時間がない人はどうする
部活などで忙しい人は、どうしても学習時間が短くなります。
限られた時間の中で効果を上げるためには、工夫が必要です。
体系問題集をなるべく短い時間で学習するには、■の問題だけ先に解きましょう。
■の問題だけ解けば、一通りの学習ができるように問題集が構成されています。
日頃は■の問題だけ学習して、試験前に残りの問題も一気に解いてしまえばどうでしょう。
テストで点数を取るのが目的であり問題を解くのが目的ではありません。
テスト前の体系数学の学習法
テスト前は、前に解いた時に解けなくってチェックがつけてある問題を中心に学習してください。
問題によっては、何度やっても間違うものがあるはずです。
そんな問題は、チェックが複数ついている筈です。
出来るまで粘り強く反復することが大切です。
余裕がある人は、友達に教えてもいいと思います。
人に教えるには自分がきちんと理解していないと出来ないことです。
意味が無いように見えることですが実はいい学習法になるのです。
あなたの友達も助かりますしね。
逆にいまいち理解してない人は、学校で数学が得意な友達を捕まえて解説してもらいましょう。
体系数学でよくある質問
体系数学でみんなが困っている単元はどこですか?
体系数学2幾何の相似の単元は、苦手な人が多いと感じています。そもそも、証明自体が苦手な人が多いです。
合同の証明までは何とか頑張っていたのに、相似が入ってくるとお手上げ・・・
相似を複数回使って解く問題になると訳が分からなくなる人が多いです。
関数の単元も苦手意識の強い人がいます。
単純に直線の式を求めたりは出来るけど、応用問題は苦手
特に動点処理が入った問題が出来ない人を多く見かけます。
円の単元も苦手な人が多いです。
それまでに習った相似が混ざっているので複雑になると・・・
同一円周上にある4点を見つけないと解けないような問題は、どの生徒さんも最初は戸惑います。
問題演習を重ねれば、何とかなるたぐいのものなのですが。
体系数学2代数だと2次関数が入っています。
2次関数には、放物線と直線が交わっていて面積に関連した問題になっているものがあります。
ここで急に等積変換など幾何の考え方をを使ったりします。
代数なのに幾何が関連しており、幾何が苦手だと理解不十分に陥ります。
体系数学3以降は、高校生の内容です。
勉強をさぼった人は、だんだん分からなくなっていきます。
逆に、ちゃんと学校の授業に沿って勉強している人はそこまで困らないはずです。
数学苦手ですが勉強すれば何とかなりますか?
ちゃんと勉強して克服できないことはほとんどありません。
計算力がない人は、計算力を付けましょう。
応用問題が解けない人は、何度も繰り返し解いて解法を自分のものとしましょう。
学習量はもちろん必要です。
勉強しないでできるようになることはありません。
家の近くに体系数学を教えてくれる塾がないのですが・・・
ある程度までは、自分一人でも勉強可能です。
その場合、一度解いただけで出来るようになったと思わないでください。
テストで高得点を取っている生徒さんは、できなかった問題の解きなおしをやっています。
中には3回もやっている生徒さんがいました。
自分一人ではなかなか勉強できる自信がない人はどうすればいいのか??
個人指導シグマのオンライン授業をご利用ください。
主にzoomを使っております。
p.s.2024年度から動画サポートを始めています。これにより理解できなかった問題も何度も自分のペースで動画で復習できます。
動画サポートとは
個人指導シグマで実施している動画サポート
2023年途中から一部のモニターさんたちに協力しながら実施していました。
内容を簡単にまとめると
1回の授業では、理解しにくい問題などの解説を動画にして生徒さんに配布
生徒さんは、いつでもどこでも何度でも見ることができます。
これにより問題の理解がぐっと深まり、テストの点数もUPしました。
中学2年幾何 2学期中間⇒2学期期末 +30点
中学2年代数 2学期期末⇒3学期学年末 +25点
他にも、国立大学付属の生徒さんには、学校で扱う普通の問題集には載っていない特殊な問題の解説を動画で配布しました。
すると、正解率10パーセントの問題で複数の生徒さんが得点しました。
生徒さんたちの反応も
「テスト前に復習で何度も見れるからいい!」
「自分のペースでやれるから助かる。」
「解答見ても分からない問題でも、動画だと分かる!」
などと、概ね好印象です。
動画の作成スキルが必要ですので出来る人が限られます。
そのため、対応範囲が決まっています。
基本的には、中学1年生から高校1年生までの数学です。
中高一貫校で使われている教材がメインです。
その他は、生徒さんの基部が多いものを作っております。
動画サポートの効果は、立証済みです。
体系数学の補習をオンラインでやりたい生徒さんに特におすすめです。
体系数学の問題の中には解答を見てもよくわからない物があります。
特に幾何にはそんな問題が多いはずです。
個人指導シグマでは、多くの中高一貫生を見ていますので体系数学の指導に慣れております。
体系数学でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
電話:03-5395-0949
メールでのお問い合わせは下のボタンからどうぞ!