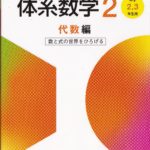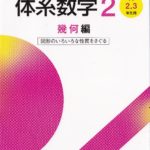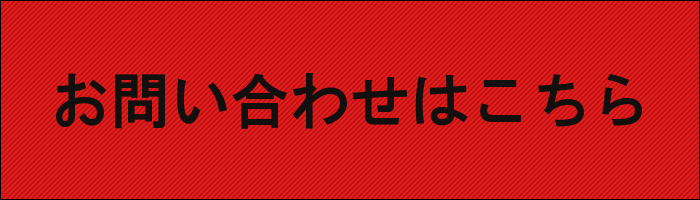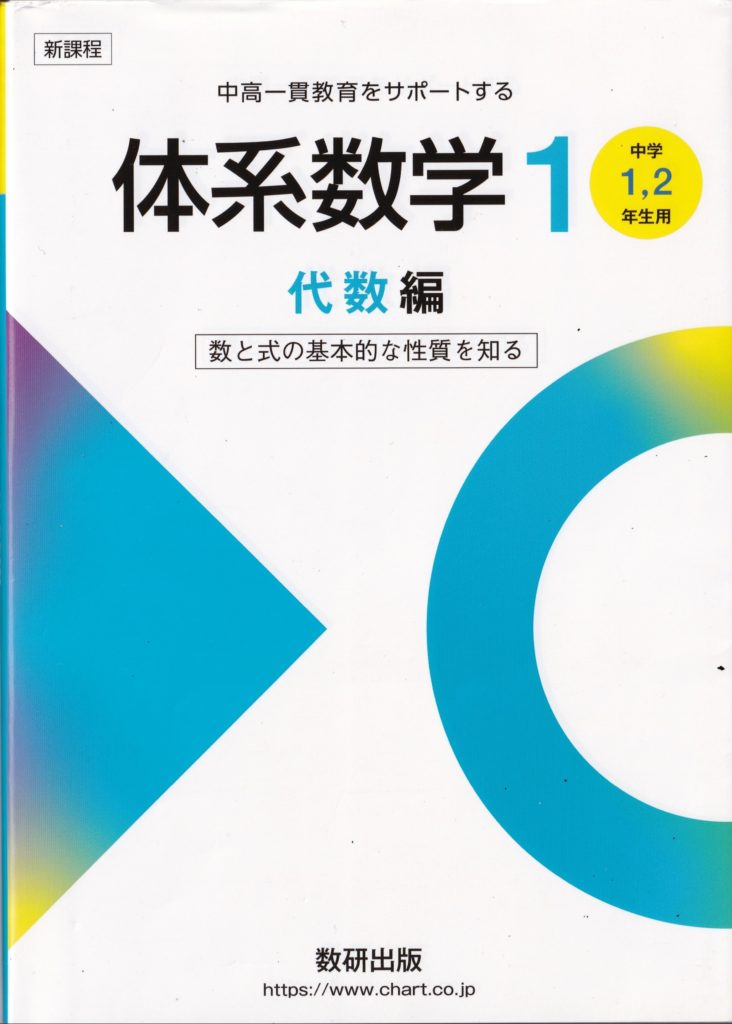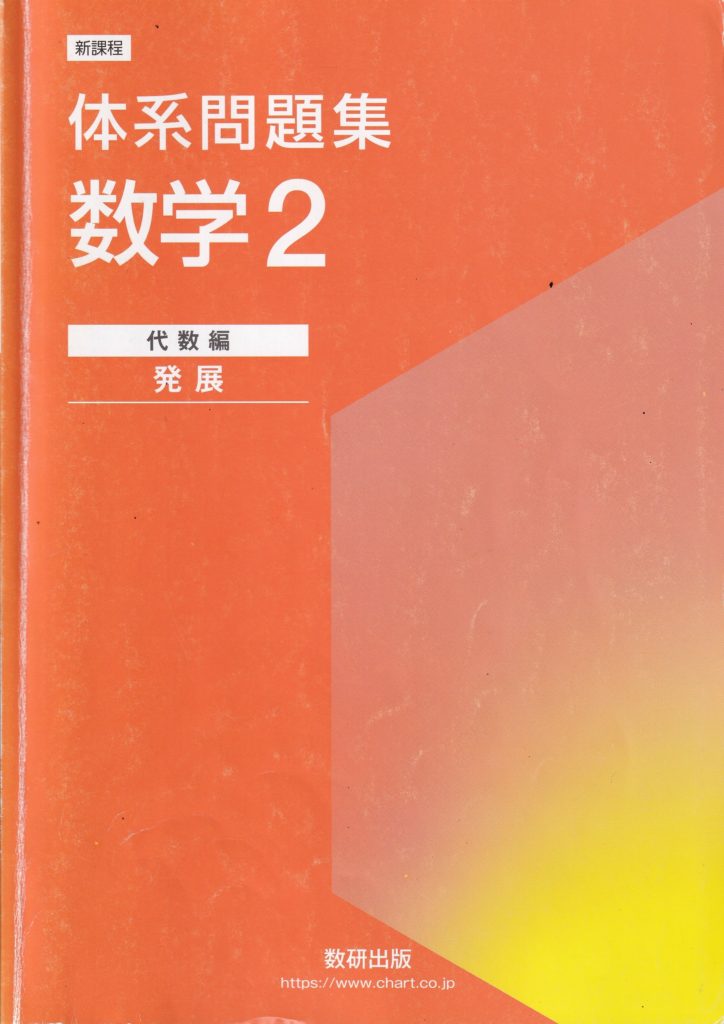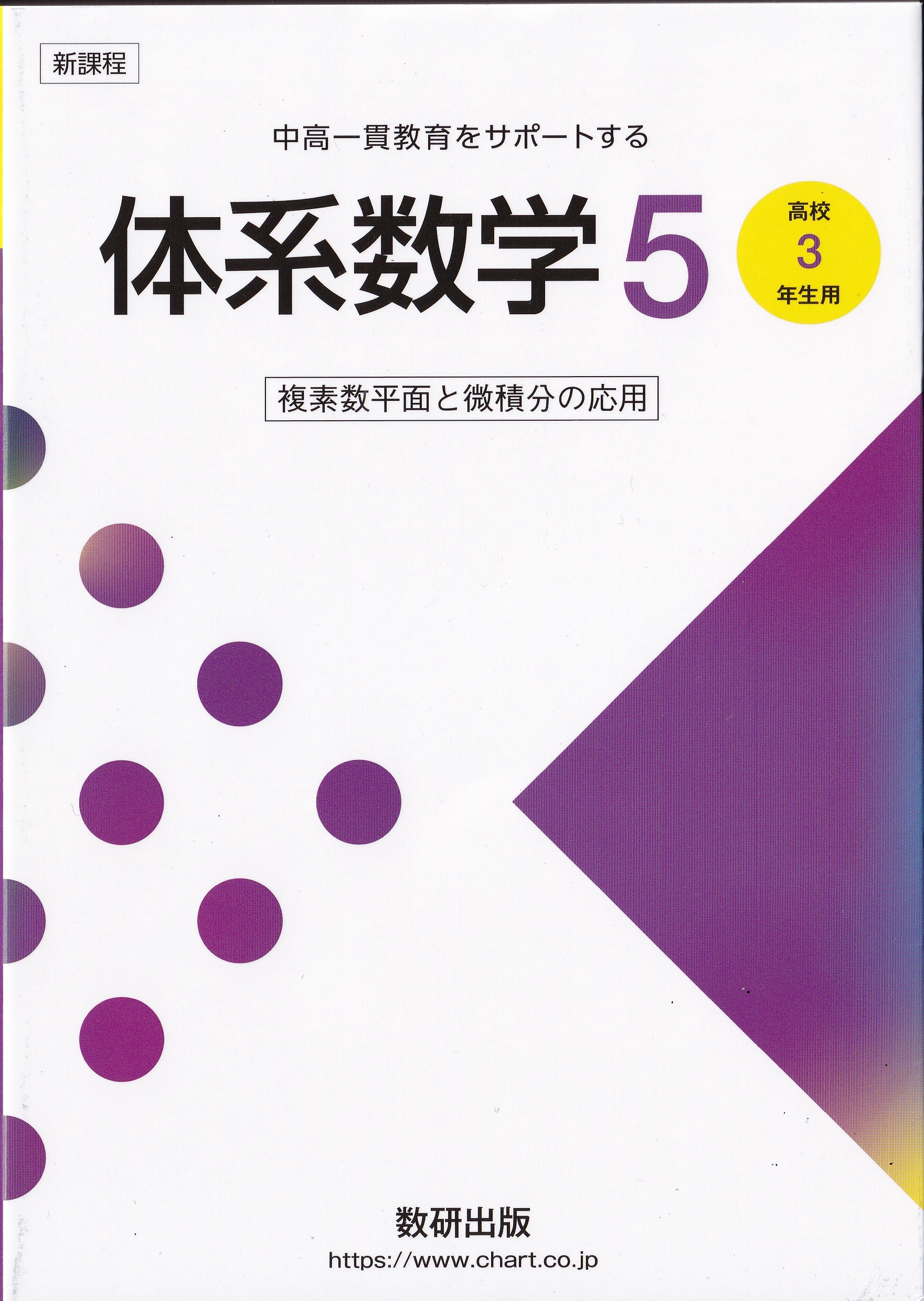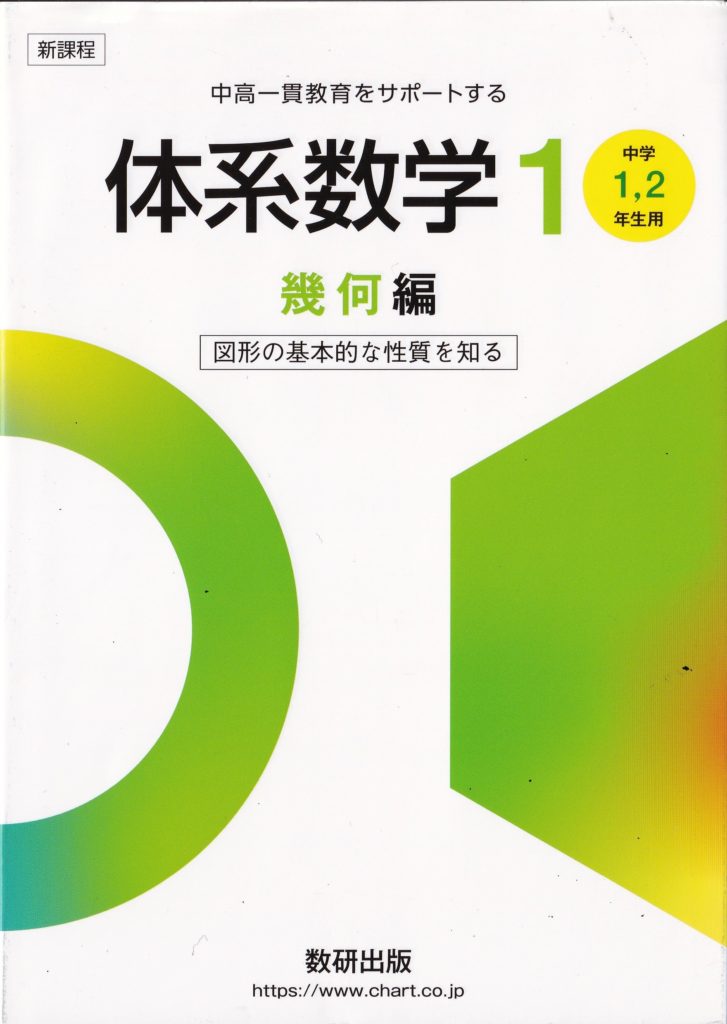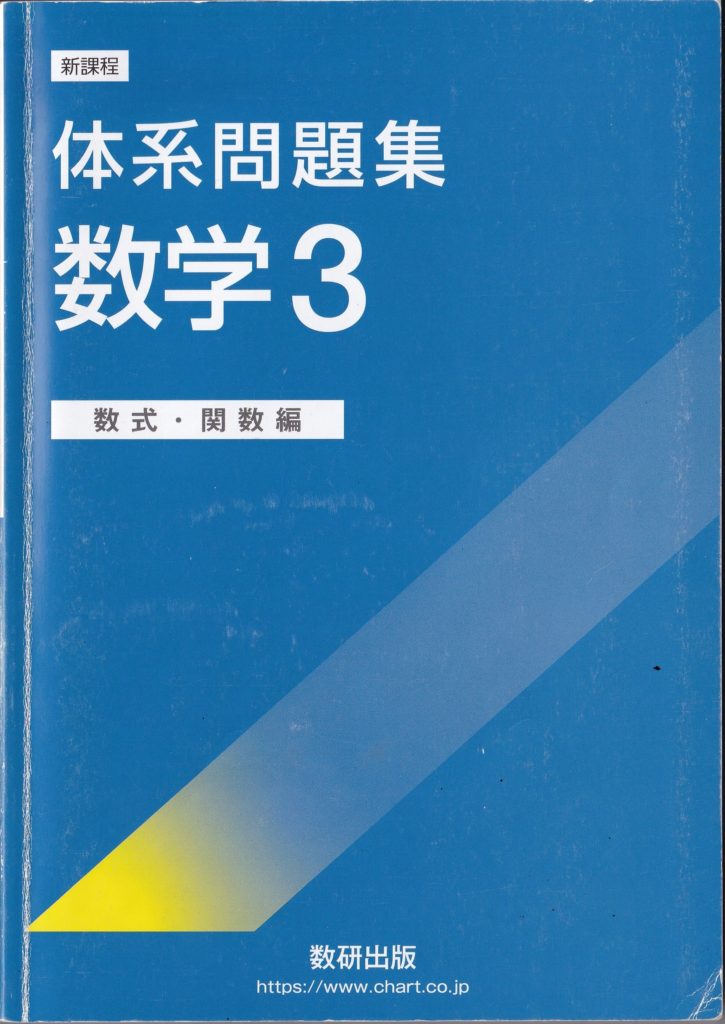
中高一貫校で使われる数学教材といえば体系数学です。
関東圏では、半分以上の中高一貫校で使われています。
特に1巻と2巻の使用率は高いですね。
2巻までで検定教科書3年分の内容が入っています。
体系数学は、内容が豊富なので、授業についていくのも大変です。
体系数学のまとめはこちらから
体系数学の特徴
体系数学は中学の内容を早く学習することが出来る教材です。
先取り用の教材とも言います。
勿論、学習スピードは各学校によって違います。
でも、中学3年生の途中ぐらいには大体の学校で体系数学2までの内容を終わらせています。
進みの速い学校では、中学2年生の2学期で体系数学2が終わります。
体系数学2で公立中学の3年間の内容と一部高校の範囲を学習出来ます。
体系数学3以降も検定教科書の並びとは、若干違っています。
でも、高校生の分野に関しては内容はそんなに変わりません。
体系数学2までの内容をちゃんと理解していれば、中学校の数学の内容は理解していると言えます。
体系数学代数2
第一章 式の計算
第二章 平方根
第三章 二次方程式
第四章 二次関数
第五章 確立と標本調査
体系数学幾何2
第一章 図形と相似
第二章 線分の比と計量
第三章 円
第四章 三平方の定理
体系数学の問題集
体系数学には問題集があります。
ほとんどの学校は発展版です。
この問題集に入っている問題は難しいものもあります。
特に図形に関しては、検定教科書とは比べ物になりません。
幾何2では、チェバやメネラウスも当たり前に出てきています。
高校生の教科書のような感覚で見るとちょうどいいと思います。
発展版を使っている学校が多いですが、標準版を使っている学校もあります。(発展版から標準版に切り替える学校がいくつか出てきています。ex.白百合)
AMAZONなどでも体系数学の問題集を購入できます。
でも、学校で使っている問題集とは内容が違います。
問題集は、定期テスト当日までに指定個所を解いて提出することが求められることが多いです。
別冊の解答を貰っていることが多いので解答を写すことも出来ます。
でも、ちゃんと解いておかないと試験の結果が悲惨なことになるでしょう。
日ごろの学校の授業に沿って問題集を解いておくのがお勧めです。
体系数学の参考書
体系数学の参考書としてはチャートがあります。
数研出版のチャート式といえばお分かりかと思います。
チャート式の体系数学版なのです。
この本の構成は、高校生用のチャート式と同じです。
体系問題集よりも難しい問題が入っています。
体系数学の問題集で苦戦している生徒さんは、無理して使う必要は有りません。
解き方が分からない時に辞書的に使うのは有りです。
何をやればいいのか?
体系数学を自分だけでやるとしたら何をやればいいのでしょうか?
それは、ご自身の理解度によって違ってくると思います。
平均点以下の人
それまでの定期試験で平均点以下の生徒さんは、基本からしっかり勉強することが必要です。
平均点以下だということは、取れる問題で落としている可能性が高いからです。
基本原理を理解して、公式を当てはめるだけの問題は確実に取れる様にする事から始めましょう。
基礎の部分を疎かにすると、平均点以下どころか赤点ラインが気になるようになります。
学校の授業を聞いてあまりよくわからなかった生徒さんは、教科書をもう一度見てみましょう。
教科書の例題だけでも解いてみるといいと思います。
大体の内容が分かったら、問題集で基本問題をやってください。
例題の下にある問題は、例題と同じ解き方です。
例題を理解しているかどうかの確認に使えます。
教科書の例題及び例題直下の問題が解けるようになったら章末にある確認問題です。
確認問題がちゃんと解ければ、大体の学校の赤点は回避できるはずです。
もっと点数が取りたかったら、その次は演習問題にも取り組みましょう。
ここまでくると大分難しくなっています。
体系問題集に関しては、提出がある筈なので普段からノートに解いておきましょう。
それをやった上で、テスト前は出来なかった問題を出来る限り解き直しです。
目標は全部の問題が解けるようになること!
成績上位の人たちは、当たり前のように全部解けるまで反復しています。
平均点以上の人
平均点位は、いつも定期試験で取っている生徒さんは、問題集中心で勉強を進めましょう。
勿論、教科書の問題は出来るという前提でです。
教科書の問題で出来ないものが有ったら、それは勿論復習して出来る様にしないといけません。
体系問題集は、ノート提出を前提にして提出用のノートにやっていきましょう。
そうすれば試験前に慌てることがなくなります。
ノートでなく提出用の体系問題集全問の冊子を貰っている学校も有ります。
そんな学校の生徒さんも間違った問題は、問題集に印を付けておきましょう。
出来ない問題だけを拾って、2周目の復習が出来ます。
出来なかった問題に印を付けて解き直すのは当たり前です。
冊子を埋めただけで、出来る様になったと勘違いする生徒さんが意外と多いからビックリです。
ある程度やったら答え合わせとやり直しは必須です。
よく問題だけ解いて満足している生徒さんがいます。(丸付けをしない)
間違った問題を、できるようにしないと点数にはつながりません。
応用問題を避ける生徒さんもよく見かけますが危険です。
体系数学の応用問題の中には、何度も同じところで間違える問題があります。
”同じ無酢を繰り返す”そういう生徒さんを何人も見てきました。
最初は、難しくとも、何度かやっていると分かるようになるのが普通です。
挫けずに何度もやりましょう。
諦めたらそこで・・・・終了
早めに全部の問題を解いて、自分の理解度を把握した方がテスト前に慌てなくってすみます。
分からない問題があったら
体系数学の解答は、比較的丁寧にできています。
でも、それを見てもわからない問題もあるかもしれません。
特に幾何の証明問題は、解答を見ながら考えないと理解できないことが有ります。
そういった問題をそのままにしてはいけません。
なるべく早く疑問点は解消しないといけません。
自分で解答を見て理解しようと考えるのは当たり前
それが出来ないようなら家族に聞きましょう。
それでもだめなら学校の先生を使いましょう。
中には忙しい先生もいるでしょう。
そういう時は先生に「いつなら教えてくれますか?」と聞けばいいと思います。
数学の得意な友達に聞くのもアリです。
自分である程度納得出来たらもう一度解いてみましょう。
分かったと出来るは全く別物です。
注意;一部の学校では解答が渡されておりません。宿題を提出したら解答をもらうシステムになっているようです。
なんでも、解答をそのまま写してしまう生徒さんが多いのでその対策だとか・・・
こういった学校では、体系数学の問題を十分に理解できないことがあります。
問題が難しいのに詳しい解答がないのですからしょうがないですね。
こういった学校の生徒さんには、シグマの授業の時に分からない問題をどんどん質問してもらっています。
テスト前は何をやれば?
普段から問題集をちゃんと解いている生徒さんならば、出来なかった問題をできるまでやりましょう。
一番効率がいいやり方です。
これをやるには、間違った問題にマークをつけておかないといけません。
普段全く問題集をやっていない生徒さんは、問題集をなるべく早く終わらせましょう。
間に合わないからといってノートを提出しないのはあり得ないです。
部活が忙しく全部解く余裕がない生徒さんは、■の問題だけとりあえず解きましょう。
これで一通りの学習になります。
実力テスト対策は
学校によっては実力テストを年に何回かやるところがあります。
業者の模試などが多いです。
そちらの対策としては、普段使っている体系数学の問題集の解き直しでもいいでしょう。
それ以外には、チャート式の体系数学の例題だけを解く方法もあります。
普段は問題集の方を優先した方がいいのですが、長期の休みなどにはチャート式を使っても復習にはいいと思います。
学校で休み中の宿題が出ます。
そちらは宿題なので勿論やりましょう。
数学の学力を伸ばしたい人は、個人的に復習をすることが必要です。
体系数学の学習が不安な生徒さんは
個人指導シグマは、ほとんどが中高一貫校の生徒さんです。
なので、体系数学はおなじみの教材です。
オーダーメイドの個人指導なので学校に合わせて学習できます。
分からなくなる個所も大体分かっています。
学校の授業で理解できない人は要注意です。
自分一人では理解できないことが多いです。
そんな時は、中高一貫専門の個人指導シグマにお気軽にご相談ください。
よくある質問
計算ミスが勉強しても減らないのですが、どうすればよいですか?
計算ミスは、減らさないと得点に響きますね。
高校生の内容に入ると計算力の違いが如実に表れます。
計算ミスが出る原因は人それぞれです。
しかし、同じようなところで毎回間違っていたりします。
ということは、自分がミスをするところがどこなのかを把握していればよいのでは?
そうすれば、計算ミスのかなりの部分を防ぐことができるということではないでしょうか。
計算問題を解いたらすぐに解答を照らし合わせてください。
〇☓だけをつけているだけでは、進歩しません。
間違いを間違いのまま放置しないことが大事です。
幾何の問題の解答を見ても難しすぎて理解できません。どうすれば理解できるようになりますか。
実は、解答を見ても理解できないという方多いです。
よく生徒さんに話を聞いてみると
「解答が長すぎて読む気がしない。」
「文字ばっかりだからよくわからない。」
と言った意見が多いのも事実です。
幾何の問題は、図を描くことが基本です。
問題文をよく読んで図を描きましょう。
仮定などの条件を書き入れるのもあたりまえ!
解答と図を照らし合わせながら、ゆっくり考えてみましょう。
全然理解できないといったことは、あまり無いはずです。
幾何の問題の証明問題が苦手です。
証明問題を学習し始めた当初は、苦手な人が多いです。
幾何の学習が進むにつれて証明のやり方にも慣れてだんだんと気が手意識が薄れていきます。
しかし、やはり幾何の証明問題が苦手な人が多いのも事実です。
証明問題を克服するために必要なことは何か?
それは、とにかく問題を解くことです。
幾何の証明問題が苦手って言っているあなた
食わず嫌いになっていませんか?
自分が解けるレベルの問題でいいのでとにかく解きましょう。
そして毎日続けましょう。
継続して学習すれば克服できないものなどありませんよ!
個人指導シグマの動画サポート効果有ります
個人指導シグマでは、体系数学の動画サポートをやっております。
全部と言う訳にもいかないので、何回も質問がある難しい問題を中心に作成しています。
生徒さんは、何度も繰り返し見る事が出来るので、復習が自分で何度も可能です。
自分の好きな時に出来るのでとても便利です。
動画サポートは、2023年から一部の生徒さんで運用テストをしていました。
利用した生徒さんの点数はかなり上がっています。(科目によっては、40点UP)
利用の仕方は、テスト前に復習で使う人がほとんどです。
数学が苦手で平均点に達していなかった生徒さん二人とも平均を軽く超えてきました。
自分で体系数学を勉強したい生徒さんにお勧めですが、個人指導シグマの会員の方だけが利用できます。
数学を何とかしたいけど、一人ではなかなか勉強が進まない生徒さんにぴったりです。
個人指導シグマは、中高一貫校専門の個人指導です。
首都圏の中高一貫校の過半数では、体系数学が採用されています。
個人指導シグマで指導中の数学教材も体系数学が殆どです。
体系数学でお困りの方は、個人指導シグマまでお気軽にお問い合わせください。
オンラインでの授業も用意していますので遠方の生徒さんも利用できます。
電話での問い合わせは03-5395-0949まで。