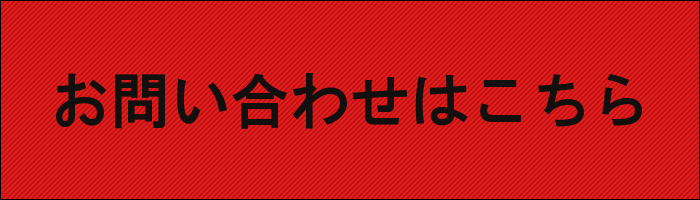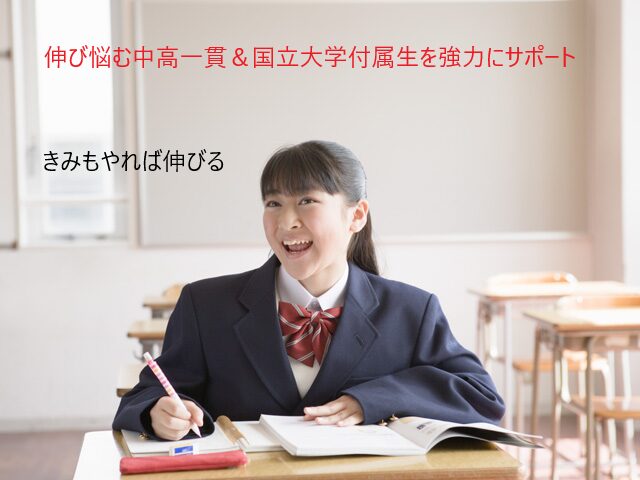”数学だけはどうしても苦手だ!”
”古典が分からないけどやる気が起こらない”
”英語が平均点全然行かないけどこれで受験できるのかな?”
皆さん、一つや二つは身が手科目がありますよね。
苦手科目を何とかしたいと考えている方も多いと思います。
でも、なかなかできるようにならないのが常ですね。
そんな苦手科目を夏休みの間に克服する方法を・・・
何故苦手なのか
とにかく嫌い
いやだ・・・・・・・・・・・・
いやだ・・・・・・・・・・・・・・・
いやだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
嫌いだからやらない。
そうすると、ますますできなくなってどんどん嫌いになる。
まさに、負の連鎖です。
放置しておいても構わない科目ならば無視しましょう。
でも、そうでない場合はちょっと考えないといけませんね。
”嫌い”という言葉で逃げてもいられないことを理解しないといけません。
結局勉強していない
勉強していたらある程度は取れます。
要は、やっていないのが原因です。
やればいいのです。
まずは少しでも・・・
一歩踏み出せるかどうかが一番大事です。
やっても理解できない
理系科目にありがちな状況です。
数学や物理、化学がどうしても理解できないことってありますね。
小学校から算数が苦手な人だと理系科目は全般的に苦手なことが多いです。
でも、自分の進路希望に必要な科目ならばなんとかしないといけませんね。
まずは、できるところから始めましょう。
出来るところを先にやると、残った所はそんなに多くないことがあります。
最後まで残ったところは、ほかの方法が必要です。
量が多すぎて覚えきれない
文系科目で多いです。
日本史や世界史さらには英語でこういった状況が出てきます。
”困難は分割せよ”
常識ですね。
まとめて何とかしようとするから大変で処理しきれないのです。
自分が出来る分量に分割してから手を付けましょう。
最初から諦めてる
苦手が苦手なのは、諦めている場合も多々あります。
本人が諦めているケースでは、苦手科目は苦手科目のままです。
本当に諦めているのか?
それとも、勉強したくないから諦めているふりをしているのか?
どちらにしても諦めたら、そこで試合終了・・・・・・・・・・
どうやれば苦手を克服できる?
その科目の重要性を確認
苦手科目は一般的に興味がないものです。
自分の視野外にあったりします。
苦手科目の教材は一番下に埋もれていたりもします。
苦手科目をそのままにしないためには自分の意識を変えないといけません。
その科目が出来ないと自分にとってどれだけ不利益になるのかを調べてみましょう。
受験科目に入っている教科だと捨てることは普通は許されません。
共通テストだけの科目であれば、ちょっと状況が違います。
ほかの科目でカバーできるようならばそんなに力を入れなくともよいことも。
そうでないのならば、ちゃんとやらないといけないことを自覚することが必要です。
自分の実力を客観的に判断する
”やればできるから”
こんなこと言っていませんか?
やれば出来るのは当たり前です。
やるかどうかが問題なのです。
やれば出来る子もやらないとできない子のままです。
残念な子にならないためにも一度自分のその科目の実力を冷静に評価してみましょう。
”どのくらいわかっているのか”
目標の設定
自分の実力が分かったら到達したいゴールの設定です。
とりあえずは、夏休みの終わりまでにどうなっていたいのか?
なりたい自分をイメージしてください。
かかるであろう学習時間の割り出し
目標を設定したっらそれに必要な時間を見積もりましょう。
ここでは正確である必要はありません。
あくまでも大体の時間です。
大体の時間を見積もってその時間を夏休みのどこに割り当てるのかを考えるのです。
計画
目標を設定してもそのままでは絵に描いた餅です。
目標を達成するには計画が必要です。
計画の立て方はこちらをご覧ください。
実行
計画倒れで終わらないようにするには実行しないといけませんね。
いや、実行が一番大切ですね。
計画を立てす前にちょっとやってみましょう。
そうすると自分なりの手ごたえなり何らかの感触が得られると思います。
それから自分に合った計画に落とし込んでいってもいいと思います。
実行に当たっては、自分に合った量や時間などを考えないといけません。
自分で考えるからこそ自分に合った計画が出来るのです。
何も考えないでやっている人とは大きな差が付きますよ。
学習順位を上げる
苦手科目を克服したかったら勉強しないとどうしようも有りません。
そのためには、学習順位を上げましょう。
具体的に言うと、毎日最初に苦手科目を学習する様にしましょう。
短時間でも構いません。
少しずつでもやっていれば、前に進みます。
脱がって科目と言っても所詮は、勉強すれば何とかなります。
なぜ夏休みなのか?
まとまった時間が取れる
中学生・高校生であれば学校は休みです。
日々の授業のための勉強から解放される時期ですね。
次の日の予習や復習をしなくともいいのは気が楽です。
苦手科目の克服には時間がとられることがあります。
そういった意味でも夏休みは、苦手科目の克服にもってこいだといえます。
1学期の復習には絶好の期間
復習サイクルをご存知の方は、もううなずいていると思います。
忘却曲線を念頭に入れて学習するのならば夏休みは1学期の復習に最適です。
日々の学習、テスト前の学習をしても時間がたつと記憶はだんだんと欠けていきます。
それを夏休みに復習することで思い出すのです。
こういった複数回の学習が短期の記憶を長期の記憶への変換を促すのです。
どのくらいやればいいのか?
個人差
よくある質問ですが明確には解答できません。
それは、ご自分の理解度とゴールさらには能力差があるからです。
なんで”Aちゃんは10時間やっていたから私も”
などといった単純比較は成立しません。
重要度によるゴールの違い
前にも書きましたが、苦手科目だからといって全部やる必要はありません。
自分にとっての重要度によって力の入れ方が変わります。
受験科目であればかなり仕上げないといけません。
受験生であればなおさらですね。
国立でも私立でも必要な科目であれば捨てることは許されません。
優先順位が上です。
教材は何を使えばいいのか?
実力にあった教材が一番
教材は、自分の実力に合ったものを選ぶべきです。
受験向けのマニュアル本を見ると色々な参考書が紹介されています。
でも、あなたん実力に合わないものをやっても効果は疑問です。
問題集であれば半分ぐらいはわかる問題集が使いやすいです。
絞る
参考書は、何冊もいりません。
なるべき絞りましょう。
学校で配布されている程度の基本的な参考書がいいと思います。
何冊も使うよりは、1冊の参考書を何回も反復した方が効果的です。
人間ですのでどうしても忘れてしまうので復習が必要になるからです。
基本的には、夏休みに仕上げる本は各科目1冊以内にした方が上手くいきます。
欲張りすぎると、すぐに計画倒れになります。
全く理解していないのでどこから手を付けていいのかわからない。
とにかくやってみる
”全く分からない”
そういう風に思い込んでいるだけかもしれませんよ。
とにかく手を付けてみましょう。
大変そうに見えるものでも、やってみると大したことがないこともよくあります。
まずはやることが大切です。
少しわかるところから手を付ける
全然わからない所からではなく、わかるところから手を付けましょう。
やっているうちにやる気が出ることもあります。
やる気になってからやるのではなくやってからやる気が出るのです。
その意味でもやり易いところから手を付けることは有効です。
受験科目だけど間に合うの?
逆に間に合わせないといけないのでは?
”間に合うの?”などといっている場合ではありません。
間に合わせないといけないのではないでしょうか?
”どうやったら受験に間に合うのか”こういった目線で考えましょう。
必ず答えはあります。
割り切る
受験生ならばやるだけです。
色々文句を言ってもしょうががありません。
いいたいことは受験が終わってから言えばいいことです。
あなたに必要なのは、苦手科目を何とかすることです。
基礎の確認
焦って受験レベルばかりやってもいけない科目があります。
理解を要する科目です。
基礎に不安がある人はまずは基礎を構築することから始めましょう。
基礎が出来ていないとそのあとの学習が大変です。
特に数学は、数Ⅲに入るとそれまでの内容が分かっていないと計算ミスが多発して時間ロスが大きくなります。
以上、苦手科目の克服についてまとめてみました。
苦手科目をお持ちで何とかしたいけどどうしていいのかわからない方は、個人指導シグマまでお気軽にご相談ください。
中高一貫&国立大学付属専門のオーダーメイドの個人指導
だから、あなたに合ったやり方が見つかります。
遠方の方は、オンライン授業も利用できます。
電話:03-5395-0949