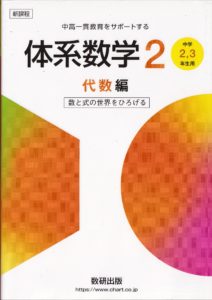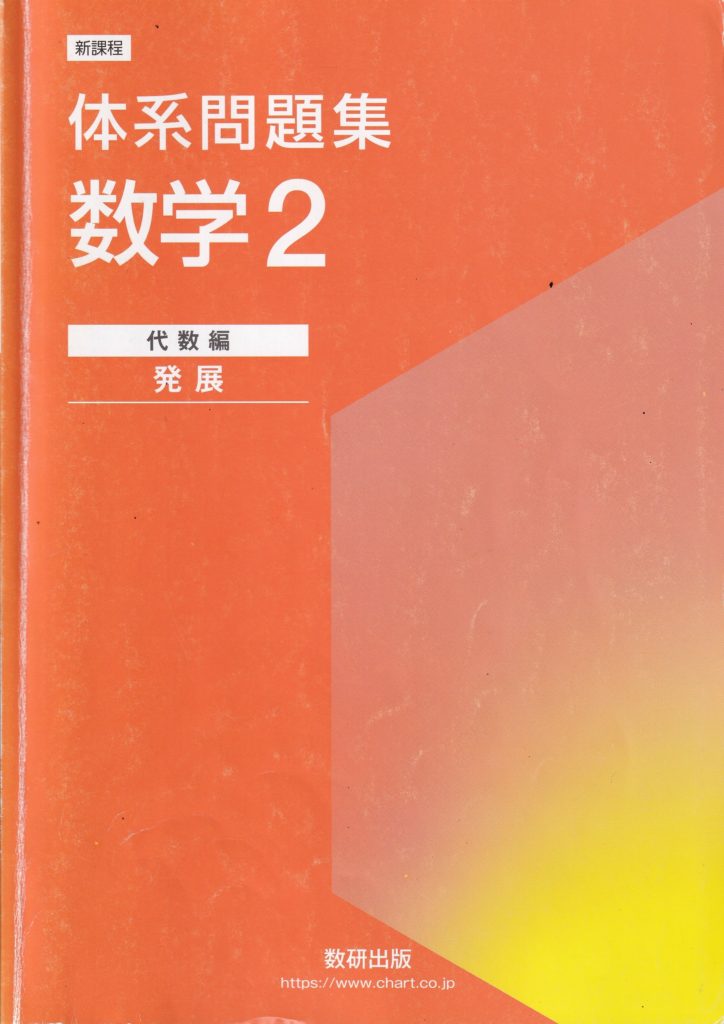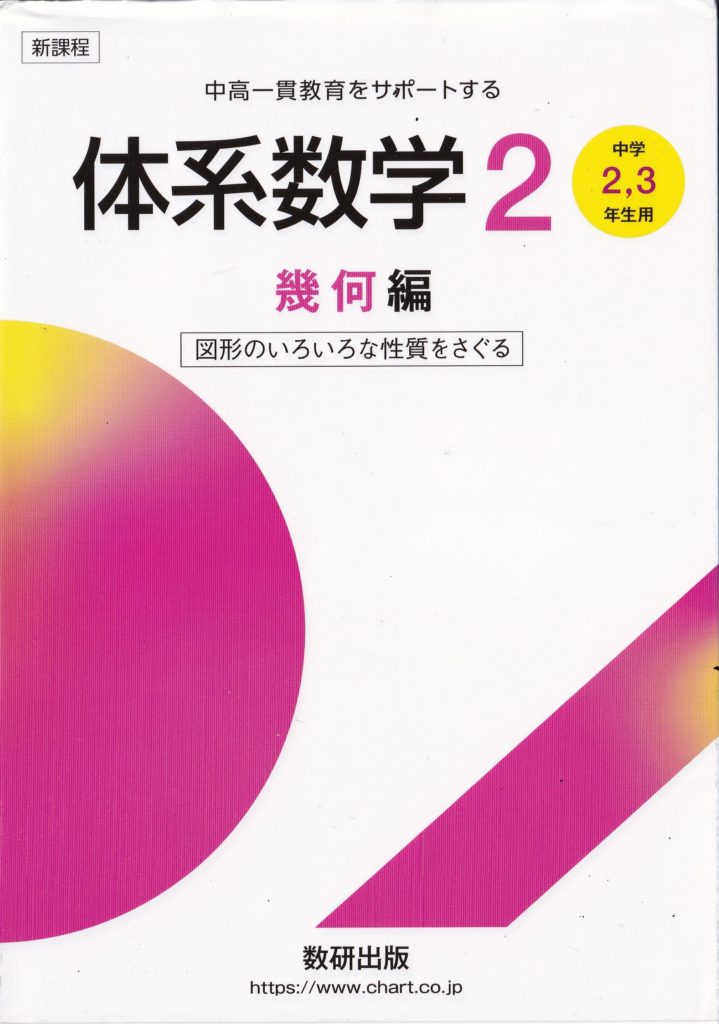
2学期は、行事も有りますが勉強も進みます。
1学期と同じペースだと思っていると足元をすくわれます。
体系数学を使っている学校の生徒さんは、油断していると授業についていけなくなります。
進みが速くなる2学期をどう乗り切ればよいのでしょう?
中高一貫校の数学教材
関東圏の中高一貫中学の教材は、体系数学が大半です。(特に中学1・2年)
体系数学は、数研出版が出している数学の教材です。
なぜ、これだけ使われるようになったのか?
それは、その構成と問題のレベルにあると思います。
高校受験がなく、大学受験が目標の中高一貫校にとっては都合の良い教材なのです。
体系数学まとめはこちら
体系数学の特徴
体系数学は、通常の文部科学省検定の教科書と違い先取り学習を念頭に置いています。
体系数学のシリーズ1・2を終わらせると、通常の中学3年分プラス高校生の内容の一部が履修できます。
つまり、2年間で公立中学3年分の内容を学習できるのです。(学校により授業のスピードが異なります。)
内容もやや高度な問題が入っているので、数学が苦手な生徒さんはしかっりと復習しないとついていけません。
中2の2学期は、体系数学2の代数と幾何を併用している学校が多いと思われますのでその内容の一部を紹介します。
幾何の方は、通常の教科書の中3の円と三平方の定理、そして高校の数学Aの円や線分比の内容になると思います。
代数は、2次方程式と2次関数が範囲です。
2学期は体系数学で何を学習する?
中学1年生
中学1年生は、代数が方程式の単元が中心です。
1次方程式と連立方程式そして不等式も
計算がちゃんと出来るのが基本です。
それに文章題も入ってきます。
進度が早い学校では、関数まで学習します。
幾何は、平面図形が終わって立体図形そこから三角形・四角形の証明へと進みます。
証明問題は、苦手とする生徒さんが多いです。
何を書けばよいのか分からなくなる生徒さんも出てきます。
中学2年生
中学2年生は、代数は2次方程式と2次関数あたりです。
1学期に学習した因数分解や平方根の理解が今ひとつだと苦労します。
計算力がないと問題が解けないのです。
文章題も勿論入ってきます。
幾何は、円が中心です。
円の分野は、相似を使って解く問題も多いので相似の範囲の理解が足りない人は・・・・
学校によっては、三平方の定理まで進むことも!
しっかり問題演習をしないとついていけない単元です。
一番大変な範囲だと思います。
体系数学の問題例
例えば、三平方の定理だとこういう問題です。
解いてみれば分かりますが、なかなか手ごわいです。(ちなみにこれは、Level C一番難しい問題)
解答も別冊でついていますが、一人で理解するのはなかなか大変です。
そんな時に使える本もあります。
チャート式の体系数学
チャート式の体系数学という本が数研出版で出されています。
類題の解法などは、参考になるかもしれません。
学校によっては、このチャート式も併用して大量の宿題を出しているところもあります。
でも、体系数学に関しては、問題集を何回もやって完璧にした方が効率がいいと思います。
いたずらに沢山やるよりも、きちんとした知識を蓄積した方が良いのではないでしょうか?(あくまでも、個人的な意見です。)
辞書の様に使うのは賛成です。
でも、全部の問題を出来る様にしないといけないと思い込むと大変です。
それが出来ればよいですが、学習量が膨大になります。
そうなると当然、こなせなくなります。
すると、ギブアップすることになります。
体系数学でお困りの方はお気軽にお問い合わせを
体系数学の幾何の問題は、ご家庭でも教えにくいと思います。
代数の範囲なら理系出身の方ならたぶん教えられます。
でも、幾何は補助線など慣れていないと思いつかないようなことが出てきます。
もし、体系数学を使っている学校に通っていて、数学にお困りの方はお気軽にお問い合わせ下さい。
皆さん、同じような所で困っています。
TEL:03-5395-0949
遠方の方には、オンラインでの指導もご用意しております。
体系数学1・2に関しては、動画でのサポートを開始しております。
多くの生徒さんが間違う問題は、動画で解説している教材を用意しています。
こちらのサービスは、会員の方のみが対象です。
動画サポートを梨世応した生徒さんは、使わなかった場合よりも理解が進みます。
何故かと言うと、自分のペースで何度も復習することが可能だからです。
個人指導シグマの生徒さんで一気に得点を伸ばした人は、動画を何度も見直して理解を深めてテストに臨んでいました。