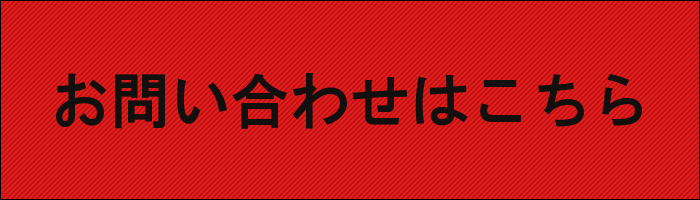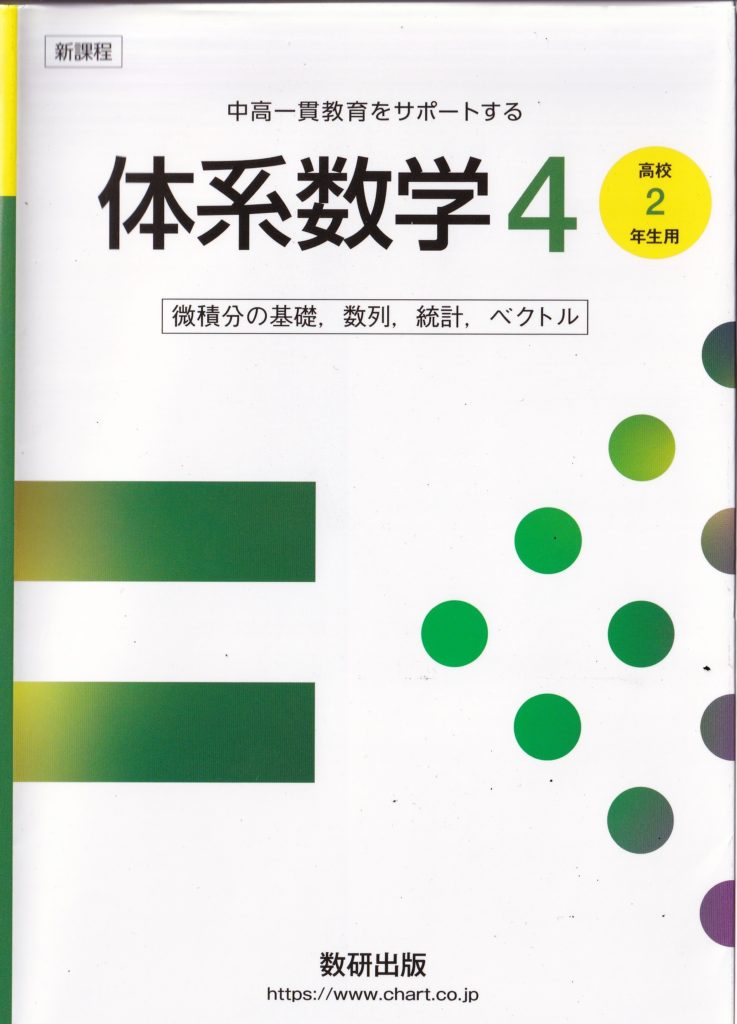
個人指導シグマの生徒さんは、中高一貫生がほとんどです。
一口に中高一貫と言ってもその内容は学校によって様々です。
色々な学校の生徒さんが来ていますので、高校1年生の12月段階の数学についてやっている内容を比較してみました。
進度が違う
速いグループ
数学Ⅰ・Aはもちろん数学Ⅱ(微分・積分を除く)も終わっています。
2学期の期末試験の範囲は、数学Bのベクトルと数列です。
3学期に数学Ⅱの微分・積分を終わらせれば、国立文系志望の生徒さんは受験で必要な数学全部を履修したことになるいます。
こういった学校では、中学2年生までに体系数学2まで終了しています。
体系数学2まで終われば、中学の範囲は全部やっていることになります。
それどころか、高校の範囲も一部学習しているのです。
理系進学割合の多い学校ですね。
関西の進学校は、ペースが速いような印象が有ります。
EX;西大和
普通のグループ
中高一貫校で普通の速さの学校では、高校1年生では数学Bまでは終わりません。
高校1年生では、数学Ⅱまで終わらせて高校2年生で文系なら数学Bだけ理系は数学Ⅲまで大体学習します。
2学期の期末試験の範囲は、数学Ⅱの最初の方か真ん中ぐらいの所になっています。
中堅校や女子高で文系進学が多い学校がこのグループに当たります。
もちろんそうでない学校もあります。
遅いグループ
高校1年生で数学Ⅰ・A
高校2年生で数学Ⅱ・B(MBはやらない学校もあります。)
理系の生徒さんは、高校3年生の1学期に数学Ⅲ
と言うように都立高校の進みと同じ速さのガッコもあります。
大学付属校や理系進学に力を入れていない学校です。
推薦での進学が多い学校もこの中に入ることになるかもしれません。
大学付属の学校もそんなに速くありません。
教材が違う
高校生の範囲になると教科書は普通の教科書を使うことが多いです。
一部の学校で体系数学3以降(白百合、フェリス)を使っています。
学校間の違いが目立つのは副教材です。
チャート式
参考書として学校で青チャートを指定されていることが多いです。
青チャート自体も試験範囲に入っている学校もいくつかあります。
普段の授業では、青チャートを使わない学校でも夏休みや冬休みなどに宿題としてそれまでに学習した範囲を出すところもあります。
最近進学実績を伸ばしている学校では、青チャートまで普段からやっているところが目立つような気がします。(あくまでも感覚的なものです。)
青チャートではなく、少し易しい黄チャートを使っている学校もあります。
受験で数学を使うのにはちょっと物足りません。
フォーカスゴールド
青チャートからの変更で使っている学校が多くなってきました。
青チャートよりも発展的な内容になっています。
受験勉強のスタートとして、フォーカスゴールドで総復習をする人もいます。
某女子高では、フォーカスゴールドと学校のオリジナルテキストだけで受験を乗り切っていることも事例で紹介されていました。(校内向け)
問題集
4STEP
4stepを使っている学校が多いです。
小石川、巣鴨、豊島岡、本郷・・・・・・・
章末問題までしっかりと試験範囲に入っています。
サクシード
ちょっと前まで使っている学校をよく見かけたサクシード。
筑波、慶応女子や大妻(?)で使われています。
問題数が4STEPよりも少ないような気もしますが、左のページの問題を教室で指導して右のページを丸ごと宿題に出来たので使いやすい教材でした。
公式が覚えられないと言っている方は、こういった基本問題から入っている問題集をしっかり解けば自然と身に付きます。
解答も詳しいものをもらっているはずです。
精説問題集
確認した中では、暁星で使っています。
早稲田高等学院や白百合でも使っていました。
難しい部類の問題集だと思います。
(使っている学校が少なくなりました。)
試験の難易度
定期試験の難易度は様々です。
問題集のレベルを超えた問題を必ず入れてくる学校もあります。
そうかと思えば、問題集そのままの問題が出題されるところもあります。
普通は、問題集から同じような問題を持ってくるところが多いです。
一般的には、進学実績が高い学校の方が定期試験も難しくなっています。
定期試験対策
学校ごとに違いがありますが、対策は同じです。
学校で配布された教材は、全部解けるようにしましょう。
それが出来ていれば基本は、大丈夫なはずです。
応用は余裕があればどんどんやってください。
本屋さんに行けばいくらでもありますよ!
FGあたりを自分で授業に沿ってどんどん解いていると、受験期になっても困らないことが多いです。
勿論、青チャートでも構いません。
よくある質問
うちの子の学校はほかの学校に比べて進度が遅いのですが、大学受験大丈夫ですか?
速さだけが問題ではありません。
受験までに合格レベルに達することが一番の目標です。
いたずらに速くしても、消化不良を起こして逆効果になります。
学校側もちゃんと考えていることが多いです。
しかし、シラバスと明らかに授業の進みが違うときは要注意です。
取り敢えず作っただけのシラバスになっていることもありました。
学校内で意思の統一が図られていない可能性があります。
進学実績を伸ばしている学校では、シラバス通りに授業が進められていることが多かったです。
予備校に通っています。学校でやっていることと全く違いますがどうでしょう?
生徒さん本人が、こなせているならば大丈夫です。
しかしながら、予備校に行っているだけになっていたりしませんか?
予備校は、ちゃんと自分で予習していかないと効果があまり上がりません。
予備校に行っているだけになっている方は、少し考えた方が良いかもしれません。
特に、学校の成績が悪い人は予備校どころでは有りません。
予備校をやめて学校の勉強に専念することを勧めます。
文系と理系のどちらに行けばよいのですか?
進路に関しては、絶対はありません。
ご本人が将来自分がやりたいことを見つけて、進学先もそれに沿って決めるのが本来の姿です。
近年、女子高でも理系進学者の割合が高くなってきています。
でも、周りに流されずに自分で決めるようにしましょう。
一案は、自分が将来やりたいことです。
なりたい職業でも良いです。
理系に進みたいのならば、数学などの基礎は固めておかないといけません。
定期試験もおろそかにしないようにしましょう。
英検とかは、取っておいた方が良いですか?
検定試験は、学習の目安になるので中高一貫校ですすめられることが多いです。
中学生の間は、短期の目標として検定試験取得もいいと思います。
大学受験に関しては、英検などの取得が合格に直結する場合とそうでない場合に分かれます。
英検を取っておいた方が良いのは。受験で有利になる場合です。
推薦などで応募条件に英検などが規定されている場合です。
学校によっても違いますが、最低でも準2級以上必要です。
英検の資格が得点に換算されたり加算されたりする場合もあります。
実際の入試で英語の試験が免除されるケースもあります。(英検準一以上位)
近年ですと上智・立教などのTEAP利用入試がそれにあたります。
一般受験だと少し微妙です。
それは、英検と大学受験問題を傾向が違うからです。
ただ、まったく役に立たないということはありません。
英検に関しては、余裕があればとればいいぐらいのスタンスです。
中高一貫生で数学でお困りの生徒さんは、個人指導シグマまでお気軽にお問い合わせください。
オンラインの授業にも対応しております。
電話:03-5395-0949